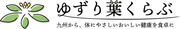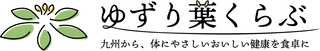アイデアブログ
飲む点滴 甘酒
甘酒は俳句でいう夏の季語。昔から夏の風物詩とされていました。甘酒にはブドウ糖やビタミン、アミノ酸が含まれ、「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養豊富。 夏バテにぴったりな飲み物です。 夏は冷たいものを飲みすぎたり、冷房に当たりすぎるなどして胃腸が弱りやすくなります。この夏は発酵ドリンク「甘酒」を身体に取り入れて暑さにも冷房による冷えにも負けないからだ作りを心がけましょう。 甘酒の種類 甘酒には、原料に米麹を使用した甘酒と 酒粕を使用した甘酒があります。 ◎米麹の甘酒・・・低カロリー。砂糖不使用の自然な甘さ。 ゆずり葉くらぶの赤米甘酒 ◎酒粕の甘酒・・・アルコールを含み、独特な香り。砂糖で味を調整するため米麹の甘酒よりカロリーは高め。 飲む目安 甘酒は飲み過ぎるとカロリーを取りすぎてしまうことも。体への吸収がいいと言われているため、たくさん飲み過ぎると体内の糖分が急激に増えてしまいます。1日1カップ(100ml~200ml)を毎日続けることがポイント。栄養補給や朝食や間食代わりに飲むのもおすすめです。体力回復やリラックスしたい方はぜひ寝る前に。 あまざけの商品ページはこちら
もっと見るもち麦って何?
もち麦とは もち麦は、大麦の一種で、粘りとコシが強く、 もちもち・プチプチとした食感が特長です。食物繊維が豊富な食材でその量は、白米の約27倍、ごぼうの約2.4倍も含まれています。ダイエット効果で話題の水溶性食物繊維の一種、”βーグルカン”が含まれいます。 なんで茶色なの? 当社のもち麦は、アントシアニンという色素が表皮に含まれているから茶色になっています。また、表皮が柔らかい品種のため、しっかり精麦しなくてもおいしく食べることができます。 炊き方 1.白米を洗って、水をいつもと同じ分量いれてください。2.もち麦を入れます。(白米1合に対して小さじ1杯より適量)3.軽くかきまぜて炊きます。※夏場は30分、冬場は1~2時間程浸水してから炊飯すると、よりおいしくお召し上がりいただけます。※雑穀米は洗わずにそのままお使いいただけますが、気になる場合は茶こしなどで軽く水洗いをしてからお使いください。 茹で方 1. 大きめの鍋に水を2Lほどいれ沸騰させます。2.中火にし、もち麦を150g入れ15~20分茹でます。3.茹で上がったらざるに上げ、流水でしっかりと洗います。ぬめりを落とすことで保存性が高まります。※もち麦150g茹でると出来上がりは約400gになります。※ボールにもち麦を入れ、30分程浸水したのちに、茹でるとよりしんまで柔らかくなり加える料理によくなじみます。※流水後は、保存容器に入れ、えごま油やオリーブオイルなど回し入れると、もち麦どうしがくっつきにくく、取り出しやすくなります。もち麦ごはんだけではなく、茹でることでスープやサラダ、ハンバーグのたねとしても活用できます。ぜひいろいろな食べ方で楽しんでください。 国内産もち麦の購入はこちら九州産もち麦の購入はこちら国内産紫もち麦の購入はこちら
もっと見る雑穀米のおいしい炊き方
おいしい雑穀米を召し上がっていただくためには、少しのコツが必要です。 ご家庭でよく使われている炊飯器を使って、簡単に雑穀米のおいしさを引き出せる炊き方をご紹介いたします。 炊き方
もっと見るNHK・あさイチで話題の「もち麦」
もち麦って何? もち麦は、大麦の一種で、粘りとコシが強く、 もちもち・プチプチとした食感が特長です。食物繊維が豊富な食材でその量は、白米の約27倍、ごぼうの約2.4倍も含まれています。ダイエット効果で話題の水溶性食物繊維の一種、”β(ベータ)ーグルカン”が含まれています。 不溶性食物繊維と水溶性食物繊維 食物繊維には「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」の2種類があります。 「不溶性食物繊維」は、水に溶けない食物繊維で、胃や腸で水分を吸収し大きく膨らみます。「水溶性食物繊維」は、水に溶ける食物繊維で、腸で善玉菌のごはんになります。 ゆずり葉くらぶのもち麦は“茶色”です。 もち麦は表皮が茶色です。この表皮にアントシアニンという色素が含まれているため、あえて表皮を残しています。また、表皮が柔らかい品種のため、しっかり精麦しなくてもおいしく食べることができます。 もち麦はアレンジもできます。 もち麦レシピ~もち麦アスパラリゾット~→材料や作り方はこちらから← もち麦のご購入はこちらから
もっと見る麹AMAZAKEをアレンジ
麹AMAZAKEのアレンジした飲み方 先日、新発売いたしました麹AMAZAKE350g。現在開催しております、新発売キャンペーンも大変好評をいただいております。そんな麹AMAZAKE350gを今回はアレンジした飲み方をご紹介いたします。 もちろんそのままでもおいしくお飲みいただけますが、いつもの甘酒に飽きてしまった方、一味変えて飲みたい方はぜひご紹介した飲み方で飲んでみられてください。
もっと見るガッテン!いま日本人がとるべきアブラ
私たちの身の回りには、さまざまな種類のアブラが存在しますが、その中で、いま日本人が一番とるべきアブラがあります。それは魚油や、えごま油など「オメガ3脂肪酸」と呼ばれるグループのアブラ。かつて日本人は魚でオメガ3を十分にとっていましたが、近年は食の欧米化もあって摂取量が減少。実はそのことが、心筋梗塞などの病気のリスクにつながることが、さまざまな研究から分かってきたのです。 でも毎日のように魚を食べるのはなかなか大変ですよね。そこでおすすめなのが「えごま油」です。1日スプーン1杯、毎日の食事に取り入れるだけで、アブラの摂取バランスがよくなり、私たちの体にさまざまな健康効果を与えてくれると言われています。 そこで、今注目の積極的に摂るべき油「オメガ3脂肪酸」についてご紹介したいと思います。 パワーの源!油の効果とは? 油(脂質)はエネルギー源となる「三大栄養素=炭水化物、たんぱく質、脂質(油)」のひとつであり、私たちにとってとても大切な栄養素です。中でも、油(脂質)は、1gあたり9kcalとエネルギー効率が高い栄養素です。 パワーの源でもある油(脂質)は、細胞膜や皮脂膜、ホルモンなどの身体を作る材料となります。また、ビタミンAやビタミンD、ビタミンEなどの脂溶性ビタミンは、水には溶けず油脂と結びつくことで吸収がよくなります。そのため、油(脂質)が不足すると、美容や健康面に影響してしまうのです。 摂るべき油の種類とバランス 普段の食事だけでは、どうしても摂取する油の種類が偏ってしまいます。大切なのは油の種類。油には色んな種類があります。中でも体内でつくることができない「必須脂肪酸」は、食事から摂らなければいけない油です。必須脂肪酸には、「オメガ6脂肪酸」と「オメガ3脂肪酸」がありますが、オメガ6脂肪酸は、加工食品など身近な食品の中に含まれているため、多く摂ってしまいがちです。一方、オメガ3脂肪酸は身近な食品に含まれていなため、不足しがちです。オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸は、4:1のバランスで摂ることが理想的と言われています。しかし、現状では20~30:1のバランスになっていると言われています。オメガ3脂肪酸を多く含む油には、えごま油やあまに油、青魚の油などを、意識して摂ることで、理想のバランスに近づけましょう。
もっと見る