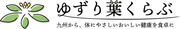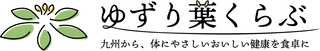大人から子供まで、みんな大好き「いなり寿司」 親しみを込めて「おいなりさん」と呼ぶこともありますよね。
「おいなりさん」とは日本の神の一つである「稲荷神(いなりのかみ)」のことを指します。 この稲荷神の遣いがキツネであり、キツネの好物が油揚げであることから、油揚げを使った寿司のことを「いなり寿司(稲荷寿司)」と呼ぶようになったという説があります。
いなり寿司には「俵型」と「三角形」がありますが、その形は東西で分かれ、 東日本の主流は「俵型」米俵に見立てて生まれた形で、対して西日本では「三角形」が主流のようで、「キツネの耳」に見立てたものだそうです。味も地域によって違い、東日本は「濃い味」西日本は「薄味」が多いようです。
「おいなりさん」とは日本の神の一つである「稲荷神(いなりのかみ)」のことを指します。 この稲荷神の遣いがキツネであり、キツネの好物が油揚げであることから、油揚げを使った寿司のことを「いなり寿司(稲荷寿司)」と呼ぶようになったという説があります。
いなり寿司には「俵型」と「三角形」がありますが、その形は東西で分かれ、 東日本の主流は「俵型」米俵に見立てて生まれた形で、対して西日本では「三角形」が主流のようで、「キツネの耳」に見立てたものだそうです。味も地域によって違い、東日本は「濃い味」西日本は「薄味」が多いようです。
材料(10個分)
作り方
①米と十六雑穀米をやや硬めに炊く。○をよく混ぜて、砂糖・塩を溶かしすし酢を準備する。
②油揚げを半分に切り、熱湯に入れ1~2分茹でて油抜きする。ざるにあげて粗熱を取り、水気を押し絞る。
③お鍋に●と油揚げを入れ中弱火で落とし蓋をして煮る。煮汁が少し残るくらいで火を止め、そのまま冷まし残り汁を吸わせる。
④雑穀ごはんが炊けたら、すぐにお釜の中で①のすし酢を回しかける。ざっくり混ぜてしめらせた飯台にあげる(バットでも可)
⑤時々上下をしゃもじで返し、うちわであおいでひと肌に冷ます。
⑥油揚げの煮汁を手のひらで軽く押して絞り、⑤のすし飯をそっと油揚げに詰め、形を整えたら出来上がり。
②油揚げを半分に切り、熱湯に入れ1~2分茹でて油抜きする。ざるにあげて粗熱を取り、水気を押し絞る。
③お鍋に●と油揚げを入れ中弱火で落とし蓋をして煮る。煮汁が少し残るくらいで火を止め、そのまま冷まし残り汁を吸わせる。
④雑穀ごはんが炊けたら、すぐにお釜の中で①のすし酢を回しかける。ざっくり混ぜてしめらせた飯台にあげる(バットでも可)
⑤時々上下をしゃもじで返し、うちわであおいでひと肌に冷ます。
⑥油揚げの煮汁を手のひらで軽く押して絞り、⑤のすし飯をそっと油揚げに詰め、形を整えたら出来上がり。
◆ワンポイント◆
油揚げは煮汁が残っている状態で火を止め、煮汁につけたまま冷ますと残った汁を吸ってジューシーでふっくらしたお揚げになります。
ぎゅうぎゅう詰めにしない方がふんわりとしたいなり寿司になります。
油揚げは煮汁が残っている状態で火を止め、煮汁につけたまま冷ますと残った汁を吸ってジューシーでふっくらしたお揚げになります。
ぎゅうぎゅう詰めにしない方がふんわりとしたいなり寿司になります。
お好みでガリやゴマなどを混ぜていただいてもおいしくお召し上がりいただけ、お弁当やホームパーティーにも映えること間違いなしです。